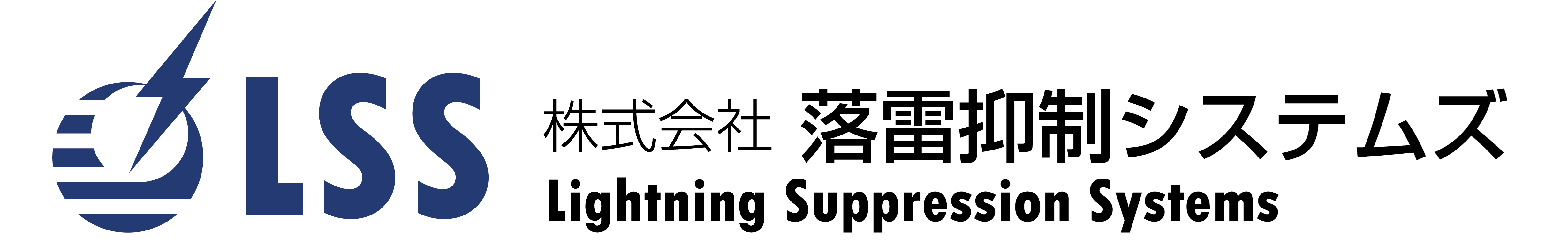落雷対策には3つの領域があります。
1.「外側」の対策
建物の外部や野外会場などを守るための対策です。落雷の直撃から建物や人を保護することを目的としています。
2. 「内側」の対策
建物内部の電気設備や電子機器などを守るための対策です。これは雷サージ(落雷によって発生する異常電圧)から内部の機器を保護します。
3.「情報」による対策
リアルタイムの雷雲接近情報をキャッチします
これらは相互に補完し合う関係にあります。重要なのは、いずれかだけでは不十分だということ。外側の対策だけを施しても、雷サージが内部に侵入すれば電子機器は損傷します。逆に内側の対策だけでは、建物自体への直撃雷の危険性が残ります。例えば、外側の対策であるゴルフ場の避雷小屋は、雷雲接近情報と併用すれば、プレイヤーをより確実に誘導することができます。適切な対策の組み合わせによって、効果的な落雷防護システムを構築してください。
ここからは3つの対策別に話を進めましょう。
外側の対策
● 避雷針
雷雲から直接建物や樹木に落ちる「直撃雷」に対しては、建物頂上部や柱上部などに「避雷針」を設置します。厳密に言うと、現在の建築基準法において「避雷針」という表現はせず、「避雷設備」と1まとめになっています。しかし、ここではそれぞれの違いをイメージしやすいよう「避雷針」と「避雷球」に分けて解説します。
まず、夏季の雷の発生メカニズムをお伝えすると、雷雲の下部にはマイナス電荷が蓄積され、この雷雲が接近することによって地面にはプラス電荷が集まります。先端が尖っている従来型の避雷針は、この原理を利用しています。雷雲が近づくと、地面に集まったプラス電荷が避雷針の先端から雷雲下部のマイナス電荷に向かって上方へ放電します(「お迎え放電」)。この放電によって雷雲からの電荷を引き寄せ、落雷を招き入れるのです。 落雷の原理
従来の避雷針の目的は、針の先端から放電することで雷を特定の場所に誘導し、地面へ放出させ、落ちる場所の雷対策を行うことにあります。
避雷針がなぜ針なのか? どうして避雷針に落ちやすいのか? その理由は全てつながっています。
針は徐々に面積が小さくなり、その先端の尖ったところで、面積は最小になります。この針の根元から伝わってきた電荷は、進むにつれ徐々に先細りとなり、針の先端では密度が一番高くなり、この先は放電するしかなくなります。ですから、放電現象を使う空気清浄機のような家電製品も放電は全て針の先端でしています。針の先からは放電するのです。
しかし、雷電流を地面に放出できたとしても、落雷の際には建物内に異常な電流(雷サージ)が流れ込みます。このサージによって建物内部の電気設備や電子機器が損傷したり、最悪の場合は火災につながったりする危険性があります。避雷針だけでは落雷被害を完全に防ぐことはできないのです。近年では、避雷針を適切に設置したオフィスビルでさえ、雷サージによる機器損傷などの被害事例が報告されています。
● 抑制型の避雷針(PDCE避雷球)
避雷球と避雷針の最大の違いは、雷を呼び寄せるのではなく、雷を寄せ付けにくくする点にあります。電極の形状が避雷針のような「突起」ではなく「半球」のキノコ型、製品によっては完全な「球型」になっているため、「避雷球」と呼ぶことで避雷針と区別しています。
落雷を招かないためには、お迎え放電をなるべく出さないことが重要です。そのため避雷球は、先端部の電極の形状を球形にして放電しにくくするとともに、絶縁体を挟んで地面からの電流を抑えて、お迎え放電が突き上りづらい構造にしています。 従来の避雷針とPDCE避雷球の違い
ちなみに、高さ20メートルを超える建築物には「避雷設備」を設置することが法的に義務づけられています。「避雷設備」は雷撃を捕捉する「受雷部」、雷電流を安全に大地に放流する「アース(接地極)」、その2つをつなぐ「引き下げ導線」で構成されています。
避雷球はこの設備の「受雷部」にあたり、雷撃を受けた場合に雷電流を安全に地面に逃がす機能はそのままに、落雷自体を抑制することで、建物内部の電気設備や電子機器の損傷、さらには火災の発生も未然に防ぐことが可能です。
内側の対策
● SPD(サージ保護デバイス
電子機器を過電圧(サージ)から守るための装置のことで、電子機器とコンセントの間や、通信機器と通信線の間などに挟んで設置する機器を指します。過電圧とは、通常の電圧を超える異常な電圧が一時的に発生する現象のことで、雷や電力系統のトラブルなどが原因で起こります。
例えば、雷が数キロ先に落ちた場合でも、電線を通じて瞬間的に何千アンペアもの電流が流れ込むことがあります。これが電子機器を直撃すると、パソコンが壊れたり、エレベーターが停止したり、最悪の場合は火災を引き起こしたりする危険性があります。
昔の電球や扇風機はシンプルな構造で、多少のサージにも耐えることができました。しかし今のパソコンやスマートフォンには小さなチップがぎっしり詰まっていて、数ボルトのサージでも簡単に壊れてしまいます。SPDはこの「サージ」をアースに流し、地中に放出することで、電子機器を守ってくれる用心棒のような存在です。
● UPS(無停電電源装置)
停電などにより電源供給がストップした場合でも、予備電力として機能してくれる装置です。パソコンやサーバーなどの電子機器と電源の間にUPSを組み込んで使用します。安全にシャットダウンすることでデータの損失を防げますし、作業内容を保存するための時間も確保できます。
通常の停電であればUPSが正常に機能して、電力会社から供給されている商用電源から蓄電池に電源を切り替え、蓄電池からの直流を後流に変換し、AC電源(コンセントから供給されている電源)が確保されます。
UPSで用意している蓄電池の容量は、一般的にパソコン1台を数十分機能させる程度です。それ以上の停電には、UPSで短時間の停電を防ぎつつ、UPSが機能している間に非常用発電機に切り替えることで、停電の無い安全な環境を継続することができます。
しかしこれが落雷を受けた場合には、UPS内の切替装置が損傷し、蓄電池への切り替えが行われるとは限りません。UPSが機能しなければ、突然の停電となっていまいます。
雷電流により、UPSが損傷して突然の停電が発生する前に、まずは雷電流をなるべく受けない対策が必要です。
● 非常用発電機
UPSは停電時に蓄電池へ瞬時に切り替わるため、停電が発生したことに気づかないほどシームレスな電力供給を実現できるという大きなメリットがあります。
しかし、蓄電池の容量には限りがあり、長時間にわたる停電に対応することはできません。数分から数時間程度の一時的なバックアップが限界であり、何時間も続く大規模な停電では商用電源の代用として機能し続けることはできません。この課題を解決するためには、UPSの蓄電池が機能している間に非常用発電機へ切り替えるという段階的な対策が有効です。
「保守が簡単に行える」「操作手順が単純である」「停電が解消されれば自動的に通常電源に復帰する」といった取り扱いやすさを選定基準とした場合、LPガスを燃料とした非常用発電機がおすすめです。
「情報」による対策
● 気象情報サービス
日々進化する気象予報技術により、精度の高い情報が私たちの身近なところにまで届くようになりました。Webサイトや天気予報アプリでも、現在地でいつ雨や雪が降り始めるかを分単位で把握できるようになっています。
雷雲が接近している場合にはスマートフォンなどにアラートで通知されたり、わずか5秒間隔でリアルタイムに更新される雷情報を確認できたりします。このような便利なツールは防災対策として積極的に活用すべきでしょう。
以下に3つのサービスを挙げておきます。
・株式会社フランクリン・ジャパン
https://www.franklinjapan.jp/
雷に関する観測とデータ提供で知られています。
正確な落雷状況をリアルタイムで確認でき、アラートとメールで通知するサービスや、72時間先までの発雷確率、雷接近危険度予測、雷発生危険度、雷雲移動方向など、雷に特化した情報が豊富です。
フランクリン・ジャパンが提供するサービスの中で特徴的なのが「落雷証明書」です。
全国雷観測ネットワーク「JLDN」の雷データを落雷証明書や調査資料、統計資料などの形で提供しています。
・日本気象協会
https://www.jwa.or.jp/service/weather-risk-management/lightning-protection-01/
主にエネルギー事業者向けの雷監視・予測サービスを提供しています。
直近〜12時間前までの落雷・雲放電の観測情報を5分ごとに、前5分間に集計した観測情報を表示する「落雷観測情報」や、1時間先までの雷の激しさと落雷の可能性(活動度)を10分ごとに表示する「雷ナウキャスト」、日本気象協会独自手法で算出した発雷確率を4段階で表示する「雷予測メッシュ」など。
利用用途に合わせて欲しい情報を選択でき、任意にカスタマイズしたアラートメールの配信も可能です。
・株式会社ウェザーニューズ
https://wxtech.weathernews.com/products/wfb/
「ウェザーニュースfor business」という法人向け気象サービスを提供しています。
施設や店舗など、複数の拠点を登録し、まとめて気象情報や防災情報をスマートフォンとPCで確認できます。
36時間先までの発雷確率や線状降水帯・豪雨リスク予測、落雷実況や過去データ、警戒が必要な時間を表示できる落雷リスクモニタリング(オプション)など、一般には公開されていない各種専門気象情報が確認可能です。
(1冊にまとめました!)リスク管理に必読! 0(ゼロ)から分かる「落雷対策完全ガイド」