「落雷被害」にも3種類あります
1.直撃雷
直撃雷とは、いわゆる「雷が落ちる」状態です。雷の放電によって電流が人体や建物、樹木などを通過します。人に落ちた場合は約8割の確率で死亡。死に至らなくても重篤な症状が残ることが多く、建物に落ちた場合は建物設備の破壊、樹木に落ちた場合は火事を発生させるなど、雷被害の中で最も甚大なのが直撃雷です。
建物以外でも電車に落雷し運休、数十万人に影響が出たり、屋外イベントのテントに落雷し大人数が負傷したりという事故も発生しており、企業の直撃雷対策は必須といえます 。
対策としては、雷を集めて落とす避雷「針」ではなく、落雷を抑制する作用のある避雷「球」が最善と弊社では考えています。
2.誘導雷
誘導雷とは、電線を流れてくる雷電流です。雷が直接落ちたわけではなく、近くで落雷が発生したときに、電磁誘導によって電線や通信ケーブル、金属製の設備に雷電流が誘導されることがあります。また雷雲が接近しただけでも地上の電線は静電誘導で帯電し、雷雲の電荷が雲中放電で失われるとバランスが崩れ、 電線にたまっていた電荷が流れ込むことがあります。
建物や樹木などへの直撃雷があると、周辺に強力な電磁界が生まれ、電磁誘導によって近くの電線やケーブルなどに瞬間的な過電圧や過電流が発生します。これを「雷サージ」と呼びます。この雷サージが電源線や大気、アンテナなどから室内に侵入し、電子機器の破壊を引き起こします。火災報知器や電話、コンピュータ、空調、テレビ、監視カメラなど、特に配線の長い電子機器に影響があります。近年は省エネルギー化や電気部品の高密度化が進み、ノートパソコンやスマートフォン、エアコンなどの小さな電圧で動く製品こそ被害を受けやすいのが特徴です。
また、さまざまな機器がネットワークでつながっているほど、雷サージの侵入経路が拡がるとともに、誘導雷の被害を受ける範囲も拡大します。
対策としては、雷サージを安全に放流することで落雷被害から電気設備を守る「SPD(サージ保護デバイス)」などを使用します。ただ、これは建物内部に設置し設備を守るためのものなので、建物外部に避雷球などを設置する直撃雷対策もセットで行うことを推奨します。
3. 逆流雷
建物や地面への直撃雷によって、雷サージが地表を流れて地面に立っている人に影響したり、アース線から建物に逆流して侵入する雷を「逆流雷」と呼びます。通信・放送設備などへ電力を供給する配電線などに発生しますし、公園やサッカー場などで付近の樹木に落雷すれば、地表を伝わって逆流雷による被害が発生します。
逆流雷の対策は、基本的には誘導雷対策と同じですが、屋外にいる人を保護するには、雷雲の接近情報をキャッチし安全な場所に誘導することです。
これら3種類の発生割合は、直撃雷1%、99%が誘導もしくは逆流雷といわれています。
ただ直撃雷は1%と数字としては低く見えるものの、その被害は甚大ですので、被害にあった場合に「対策をしていなかった」では済まされません。
また、誘導雷・逆流雷に関しても、侵入ルートは9割が不明だからこそ、複合的な落雷対策が必須といえるでしょう。避雷針があっても、それでも被害は防ぎきれません。
(参考)建物に落雷が発生した場合の被害
1)接地間電位差 落雷した電流で大地の電位が上昇し、接地を通して電気、通信系等に電流が流れ込む
電気系、通信系統に別の接地がしてあっても、これらの接地と避雷針の接地に十分な離隔距離が無ければ、避雷の接地からの電流が、地下の接地から電気系、通信系に逆流します。
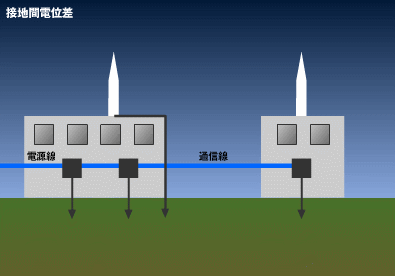
2)フロア間電位差 ビル内部の各階で電位差を生じる
ビルの各階から地面までの距離は当然異なりますから、地面を基準とした場合の各階での電気抵抗は異なります。落雷で各階を貫いて電流が流れると、この電気抵抗の違いにより各階で電位差を生じます。
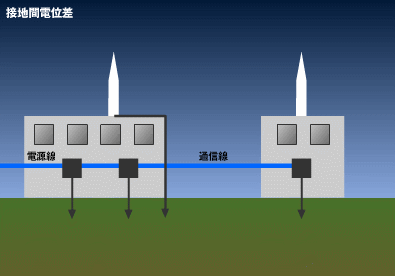
3)避雷針までたどり着いた雷が、そのままアース線を伝わって大地に流れ込むことなく、例えば、隣のビルの側面やビルの近所の構造物などに流れる。これを二次落雷と呼びます。
避雷針があれば問題は全くないというものではありません。落雷は、発生しないこと、それが一番です。

